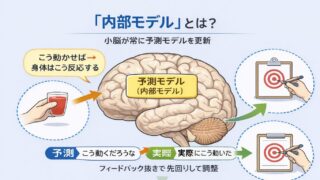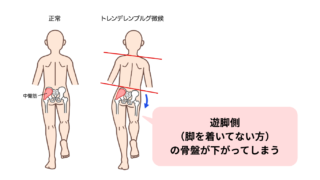寝たきり予防〜健康寿命をのばすためにできること〜

日本は世界でも有数の長寿国ですが、「元気で長生き」するためには、ただ寿命が延びるだけでなく、健康寿命を延ばすことが重要です。
特に高齢期になるとリスクが高まるのが「寝たきり」状態です。
この記事では、寝たきりの原因や予防のためにできることについてわかりやすく解説します。
関連記事
寝たきりの主な原因とは?
厚生労働省のデータ(2022年 介護保険事業状況報告)によると、要介護の原因となる主な疾患は以下の通りです。

これらは複数の因子が絡み合って進行することも多く、特にフレイル(加齢による心身の活力低下)は、寝たきりになる前段階として注目されています。
筋力はどのくらいのスピードで落ちるの?
加齢や活動量の低下により、筋力は急速に衰えます。
• 安静臥床(寝たきり状態)では、1日で1〜3%の筋力低下が起こるとされます。
→ 1週間で最大20%、1か月で50%以上も落ちることがあります。
• 特に大腿四頭筋(太ももの筋肉)は早期に萎縮しやすく、歩行や立ち上がり動作に影響を及ぼします。
このように、筋力低下は思った以上に早く進行するため、予防的な介入がとても重要です。
関連記事
【補足】サルコペニアとフレイルの違いとは?
よく「フレイル」と並んで語られる言葉に「サルコペニア」があります。
似ているようで違うこの2つの概念について整理しましょう。

つまり、サルコペニアは筋肉の問題に焦点を当てた状態で、フレイルはより広範な“心身の脆弱性”を意味します。
どちらも放置すれば寝たきりに繋がるため、早期の介入が大切です。
寝たきり予防のためのアプローチ
1. 身体活動を保つ(運動習慣)
• 散歩、ラジオ体操、筋トレなどを日常に取り入れる
• 難しい場合は、椅子に座って足踏み運動や、立ち座り運動だけでも効果あり
2. バランスの取れた栄養摂取
• タンパク質の摂取(目安:体重×1〜1.2g/日)
• ビタミンDやカルシウムも骨・筋肉の健康に重要
3. 社会参加・会話の機会を持つ
• デイサービスや地域のサロンに参加
• 認知機能低下やうつ予防にも効果的
4. 環境整備と転倒予防
• 段差解消、手すりの設置、滑りにくい床材
• 転倒は寝たきりへの直接的な引き金になるため、環境調整も重要
5. 定期的な健康チェックとリハビリの活用
• 医師・理学療法士・作業療法士など専門職による評価
• 訪問リハビリや非保険のリハビリサービスも活用可能
作業療法士(OT)視点での寝たきり予防アプローチ
作業療法士(OT)は、「その人らしい生活」を支援する専門職です。
寝たきり予防においては、以下のような視点で関わります。
1. 日常生活動作(ADL)の維持・改善支援
• 入浴・更衣・排泄・食事など基本動作の**“できる”を増やすリハビリ**を実施
• 必要に応じて福祉用具の選定や使い方の練習も行う
2. 生活行為(IADL)や役割の再獲得
• 買い物・料理・洗濯・趣味など、その人が**「やりたいこと・やるべきこと」**を大切にする
• 社会参加や家庭内での役割維持も、生活意欲や活動性の維持につながる
3. 環境調整と生活全体のバランス支援
• 自宅のバリアフリー化や福祉住環境の調整
• 本人と家族の生活スタイルに合った生活リズムの構築
4. 精神的な側面への支援
• 無気力や抑うつへのアプローチ
• 自信を失いがちな方に対し、「できること」への気づきと成功体験の提供
まとめ
寝たきりを防ぐには、日々の小さな積み重ねが非常に重要です。
身体・栄養・社会とのつながりという3つの視点からバランスよく生活を見直していくことで、健康寿命を延ばすことができます。
もしご家族や身近な方が「最近動くのが億劫そう」「筋力が落ちてきた」と感じたら、早めにリハビリや専門家に相談してみましょう。
関連記事
保険外・自費の訪問リハビリサービス【Home Reha 福岡】
神経疾患に伴う身体機能障害から、寝たきり予防まで幅広く対応