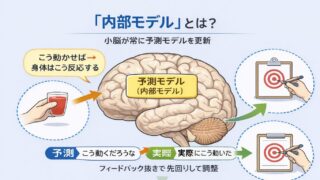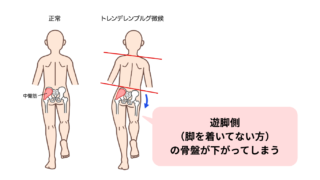肩関節を動かすと「ゴリゴリ音」がするのはなぜ?医学的な仕組みと注意点を徹底解説
はじめに
肩を回したときに「ゴリゴリ」「コリコリ」といった音や違和感を感じたことはありませんか?
リハビリや臨床の現場では患者さんから「肩がゴリゴリ鳴るのは大丈夫ですか?」という質問をよく受けます。
実は、肩関節の音の正体は一つではなく、正常な現象から病的なサインまで幅広い要因があります。
この記事では、作業療法士・理学療法士・整形外科領域の視点から「肩関節のゴリゴリ音」の原理を詳しく解説します。
肩関節の構造をおさらい
肩関節(肩甲上腕関節)は、上腕骨頭と肩甲骨の関節窩から成り立つ球関節です。
さらに、その周囲には次のような組織があります。
- 関節軟骨:骨同士が直接擦れないように保護するクッション
- 関節包・滑膜:関節を包み込み、関節液を分泌して潤滑を保つ
- 回旋腱板(ローテーターカフ):棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋から構成され、関節を安定化
- 滑液包:摩擦を減らすクッションの役割(特に肩峰下滑液包)
肩関節は可動域が非常に広いため、安定性を補うために多くの軟部組織が関与しています。
この複雑さが「ゴリゴリ音」の原因にもつながります。
ゴリゴリ音の代表的な原因
1. 腱や靭帯の引っかかり(スナッピング現象)

腱や靭帯が骨の出っ張りを乗り越えるときに「ゴリッ」とした感覚が生じます。
特に多いのが、棘上筋腱や二頭筋長頭腱が肩峰や上腕骨大結節に引っかかるケースです。
- 正常でもある程度は起こる現象
- インピンジメント症候群では強くなりやすい
- 動作の一定方向(挙上や外旋など)で繰り返し出現
2. 軟骨や関節面の摩耗

関節軟骨が摩耗すると、表面が滑らかでなくなり「ゴリゴリ」と音や振動を感じることがあります。
これは変形性肩関節症や関節リウマチに代表されます。
- すり減った軟骨が関節液中の摩擦を増やす
- 痛みを伴う場合が多い
- X線やMRIで診断可能
👉 この場合のゴリゴリ音は「摩擦音(crepitus)」と呼ばれます。
3. ガスの発生(キャビテーション現象)
関節を動かすと関節内圧が急激に変化し、関節液に溶けていたガス(二酸化炭素など)が気泡化して弾けます。
このときに「ポキッ」「パキッ」と音がします。
- 指を鳴らすのと同じ現象
- 痛みが伴わなければ生理的(正常範囲)
- ゴリゴリというより「パキッ」とした音
4. 滑液包の炎症や癒着
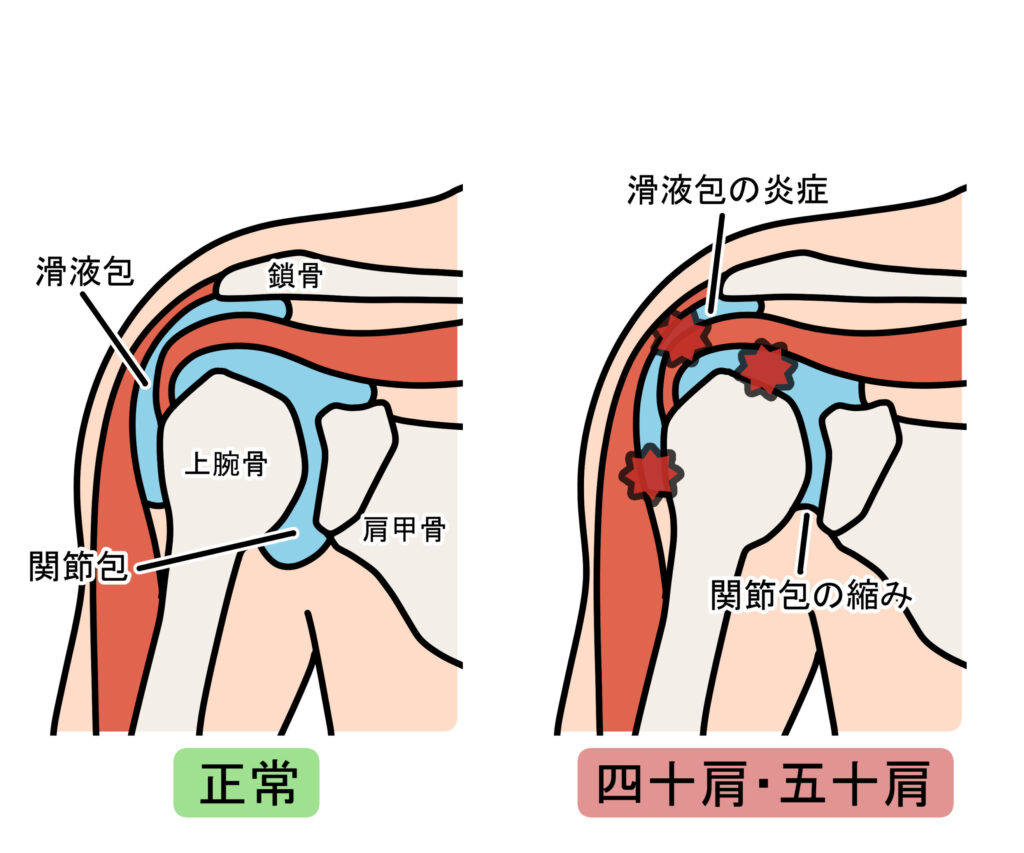
肩峰下滑液包が炎症を起こしたり、癒着して動きが悪くなると「ギシギシ」「ゴリゴリ」とした感触を伴うことがあります。
- 肩関節周囲炎(五十肩)で多い
- 動作の制限や夜間痛を伴う
- 動かすたびに軟部組織が擦れ合う
5. 瘢痕組織や線維化

外傷後や炎症後に、関節周囲の組織が瘢痕化・線維化すると動きの滑らかさが失われます。
その結果「ザラザラ」「ゴリゴリ」とした感覚を生じることがあります。
ゴリゴリ音は異常?正常?
正常の範囲
- 音がしても痛みや動かしにくさがない
- 一時的に出るだけで、すぐに治まる
- 筋肉が硬いときや疲労時に起こる
👉 多くの場合、特に問題はありません。
異常が疑われるケース
- ゴリゴリ音に痛みを伴う
- 肩が挙がらない、動かしにくい
- 夜間痛で眠れない
- 腫れや熱感を伴う
👉 これらは病的な肩関節疾患が隠れている可能性があります。
考えられる病気
- 変形性肩関節症
- インピンジメント症候群
- 回旋腱板損傷(特に部分断裂)
- 石灰沈着性腱炎
- 肩関節周囲炎(五十肩)
- 肩関節唇損傷(スポーツや外傷で多い)
これらは整形外科での診察と画像検査(レントゲン・MRI)が必要です。
ゴリゴリ音が気になるときのセルフケア
- 肩のストレッチ:僧帽筋・肩甲下筋・大胸筋をゆっくり伸ばす
- 姿勢改善:猫背は肩の引っかかりを悪化させる
- アイシングや安静:痛みが強いときは炎症を抑える
👉 ただし、痛みや可動域制限が強い場合はセルフケアだけで対応せず、早めに受診が望ましいです。
まとめ
肩関節を動かしたときの「ゴリゴリ音」は、
- 正常な範囲(腱の引っかかり、関節内のガス)
- 病的な範囲(軟骨摩耗、腱損傷、炎症)
の両方で起こり得ます。
ポイントは「痛みの有無」と「動かしにくさの有無」。
痛みや可動域制限を伴う場合は、整形外科での診察をおすすめします。