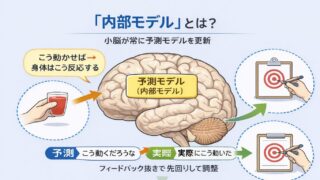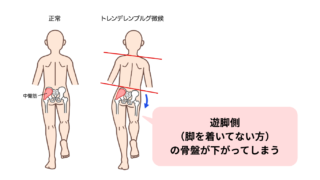手指の関節可動域訓練|柔軟性・アーチ形成・モビライゼーションの実践とエビデンス
Contents
はじめに
手指は「つかむ」「支える」「つまむ」といった日常生活のあらゆる動作に関与します。
しかし、脳卒中後や骨折後、関節リウマチなどでは可動域制限(ROM制限)が生じ、ADL(日常生活動作)に大きな影響を及ぼします。
本記事では、手指の関節可動域訓練の方法を中心に、手部の柔軟性(アーチ形成)や関節モビライゼーションについて詳しく解説し、あわせてエビデンスも紹介します。
手指の関節可動域訓練の基本
1. 他動的関節可動域訓練(Passive ROM)
- 目的:拘縮予防、関節包・靱帯の伸張
- 方法:セラピストまたは介助者が、患者の手指をゆっくりと屈曲・伸展方向に動かす。
- ポイント:
- 痛みを伴わない範囲で行う
- MCP(中手指節関節)→PIP(近位指節関節)→DIP(遠位指節関節)の順で動かす
- 1日2〜3回、各方向10〜15回が目安
2. 自動介助運動(Active Assisted ROM)
- 目的:筋活動を促しつつ、ROMを拡大
- 方法:健側手やゴムバンドを用いて患側の指を動かす。
- 例:健側で患側の指を軽く支えながら、屈曲・伸展を繰り返す。
3. 自動運動(Active ROM)
- 目的:残存筋力の強化、協調運動の改善
- 方法:
- テーブルの上で指を伸ばしながらタップする
- 握力ボールや粘土を用いたグリップ運動
- 指でタオルをつまんでたぐり寄せる
手部の柔軟性とアーチ形成
手の機能的な形態は「アーチ(弓状構造)」によって支えられています。
アーチが崩れると、巧緻性や握力が低下します。
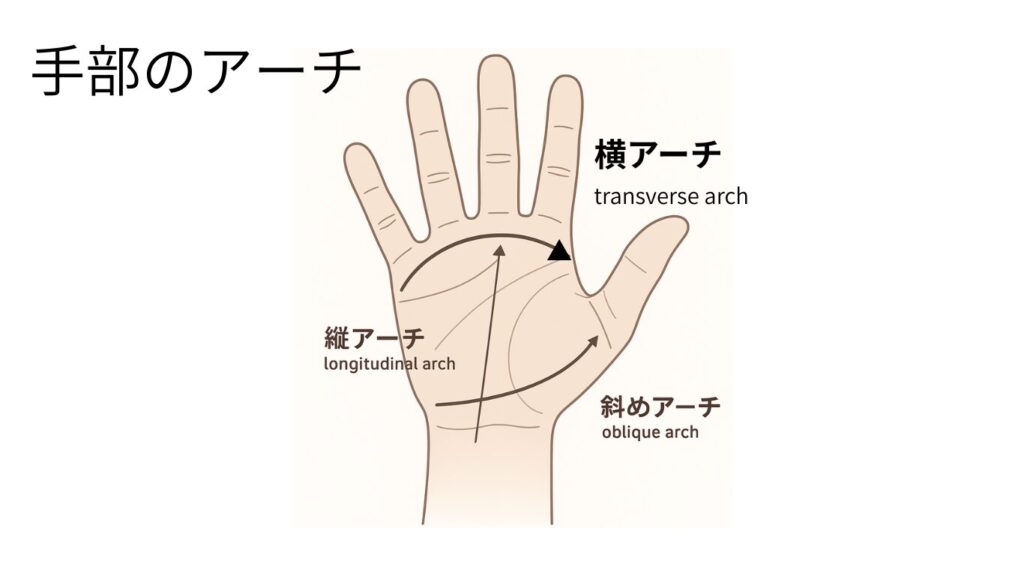
手の3つのアーチ
- 縦アーチ(longitudinal arch)
- 手首から中指方向へのアーチ
- 把握力に関与
- 横アーチ(transverse arch)
- 中手骨頭部に形成される横のアーチ
- つまみ動作に必要
- 斜めアーチ(oblique arch)
- 母指から小指にかけてのアーチ
- Opposition(母指対立)に重要
アーチ形成のための訓練
- 手掌のストレッチ:手のひらを開き、指の間を広げる
- 母指対立運動:母指を順番に各指先へつける
- タオルギャザー:タオルを指先でたぐり寄せることで、縦・横アーチを同時に強化
- クレイ運動:粘土を握ったり押し広げたりして手の柔軟性を高める
手指関節のモビライゼーション
1. モビライゼーションの目的
- 関節包や靱帯の柔軟性改善
- 関節内の滑液循環の促進
- 関節可動域の改善
2. 実践方法
- グライディング(Joint Gliding)
- 例:PIP関節を近位骨に対して掌側・背側方向に軽く滑らせる
- トラクション(Traction)
- 関節軸に沿って軽度の牽引を行い、関節内圧を低下させる
- 注意点:痛みを伴う場合は中止し、炎症がある時期は避ける。
エビデンスの紹介
- 可動域訓練の効果
- Harvey et al. (2017) のシステマティックレビューでは、他動的ストレッチは関節可動域の改善には限定的だが、拘縮予防には有効とされる。
- アーチ形成と機能
- Brandsma et al. (1993) は、手のアーチを意識したリハビリが巧緻性改善に寄与することを報告。
- 関節モビライゼーション
- Michlovitz et al. (2012) によると、手関節や手指のモビライゼーションは疼痛軽減とROM改善に有効とされる。
まとめ
手指の関節可動域訓練は、ROM制限の予防と改善に不可欠です。
さらに、手部アーチの形成や関節モビライゼーションを組み合わせることで、より実用的な手の機能改善につながります。
👉 ポイント
- ROM訓練は他動・自動・自動介助を状況に応じて組み合わせる
- アーチ形成は巧緻性の回復に直結する
- モビライゼーションは疼痛緩和と可動域改善に有効
エビデンスも示されているように、適切な評価と段階的アプローチが重要です。
臨床だけでなく在宅でも取り入れやすいため、患者教育にも役立ちます。