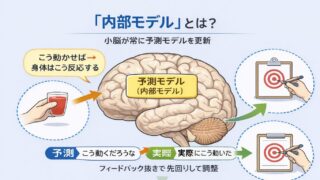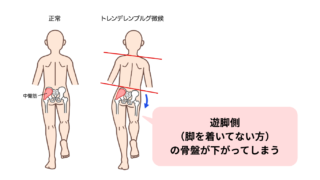【医療解説】朝に筋肉がこわばるのはなぜ?〜生理的変化と病的こわばりの違いをリハ専門職が解説〜
はじめに:朝の「体のこわばり」は誰にでも起こる

朝起きたときに「体が硬い」「筋肉がこわばって動きづらい」と感じたことはありませんか?
実はこれは、年齢に関係なく誰にでも起こる生理的な現象です。
しかし、なかには病気が隠れている場合もあるため、
仕組みを理解しておくことがとても大切です。
この記事では、
作業療法士の視点から「朝に筋肉がこわばる理由」を医学的にわかりやすく解説します。
🧠目次
- 睡眠中の筋活動と血流の変化
- 体温リズムと筋肉の柔軟性
- 筋膜・関節包の粘性変化
- 自律神経・ストレスによる影響
- 病気が原因のこわばりとの違い
- 朝のこわばりを和らげるセルフケア方法
- まとめ:起床後の動作は「ゆっくりスタート」が基本
① 睡眠中の筋活動と血流の変化

睡眠中は筋肉がほとんど動かず、体の代謝も低下しています。
そのため筋肉への血流が減り、酸素や栄養の供給が少なくなります。
- 筋肉内に乳酸や代謝老廃物がわずかに蓄積
- 関節周囲の関節液(滑液)の循環が低下
結果として、朝起きた直後には「筋肉が硬い」「関節がぎこちない」と感じやすくなります。
特に寒い季節は血管が収縮し、より強いこわばりを感じやすくなります。
② 体温リズムと筋肉の柔軟性

体温は一日の中で変化し、早朝(4〜6時頃)に最も低くなります。
体温が低いと筋肉・腱・関節の温度も下がり、柔軟性が一時的に低下します。
- 酵素反応が鈍くなる
- 神経伝達速度が遅くなる
- 関節・腱の伸びが悪くなる
→ 起床後しばらく動かしているうちに体温が上がり、
筋肉も徐々に滑らかに動くようになります。
③ 筋膜・関節包の粘性変化

筋肉を包む筋膜や関節を覆う関節包などの結合組織は、
動かさない時間が長いと一時的に粘度が上昇(ドロッとする)します。
その結果、筋膜同士や関節内の構造が滑りにくくなり、
動き始めに「硬さ」や「違和感」として感じられるのです。
この現象はリウマチの医学用語でも知られる
**「モーニングスティフネス(morning stiffness)」**に似た状態です。
④ 自律神経・ストレスによる影響

精神的ストレスや過緊張が続くと、睡眠中でも交感神経が優位なままになり、
筋肉が軽く収縮したままの状態になります。
- 肩こり
- 首や背中の張り
- 朝の腰のこわばり
これらはストレス性の筋緊張が関係していることも多いです。
寝る前のリラックス習慣(深呼吸やストレッチなど)は、
翌朝のこわばり予防にとても効果的です。
⑤ 病気が原因のこわばりとの違い
もし朝のこわばりが30分〜1時間以上続く場合は、
関節や筋肉の疾患を疑う必要があります。
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 関節リウマチ(RA) | 朝のこわばりが1時間以上続く。手指関節の腫れ・痛みを伴う |
| 多発筋痛症(PMR) | 高齢者に多く、肩や骨盤周囲の痛みとこわばり |
| 甲状腺機能低下症 | 代謝低下による全身の硬さやだるさ |
| パーキンソン病 | 筋固縮(rigidity)で動作開始が困難 |
こうした場合は自己判断せず、整形外科や内科での受診をおすすめします。
⑥ 朝のこわばりを和らげるセルフケア方法
🔹 起床時の「ゆるストレッチ」
- 布団の中で手足をゆっくり伸ばす
- 肩をすくめる→脱力を繰り返す
- 軽く背伸びや深呼吸をする
→ これだけで血流が促進され、筋肉温度が上がります。
🔹 体を温める習慣
- 朝シャワーや温かい飲み物で体温を上げる
- 寝室の冷えを防ぐ(加湿+保温)
- 寝る前に軽いストレッチや入浴で筋緊張を緩める
⑦ まとめ:朝のこわばりは「体が目覚める準備運動」
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 生理的 | 睡眠中の血流・代謝低下、体温の低下 |
| 自律神経的 | ストレスや緊張による筋収縮 |
| 病的 | 炎症・代謝異常などによる長時間のこわばり |
朝のこわばりは、体が休息状態から活動状態へ移行する「ウォーミングアップ反応」です。
多くの場合は心配ありませんが、長く続く・痛みを伴う場合は専門医へ相談しましょう。
日々のストレッチや入浴で体をやさしく目覚めさせることが、
快適な朝と健康な筋肉を保つ第一歩です。